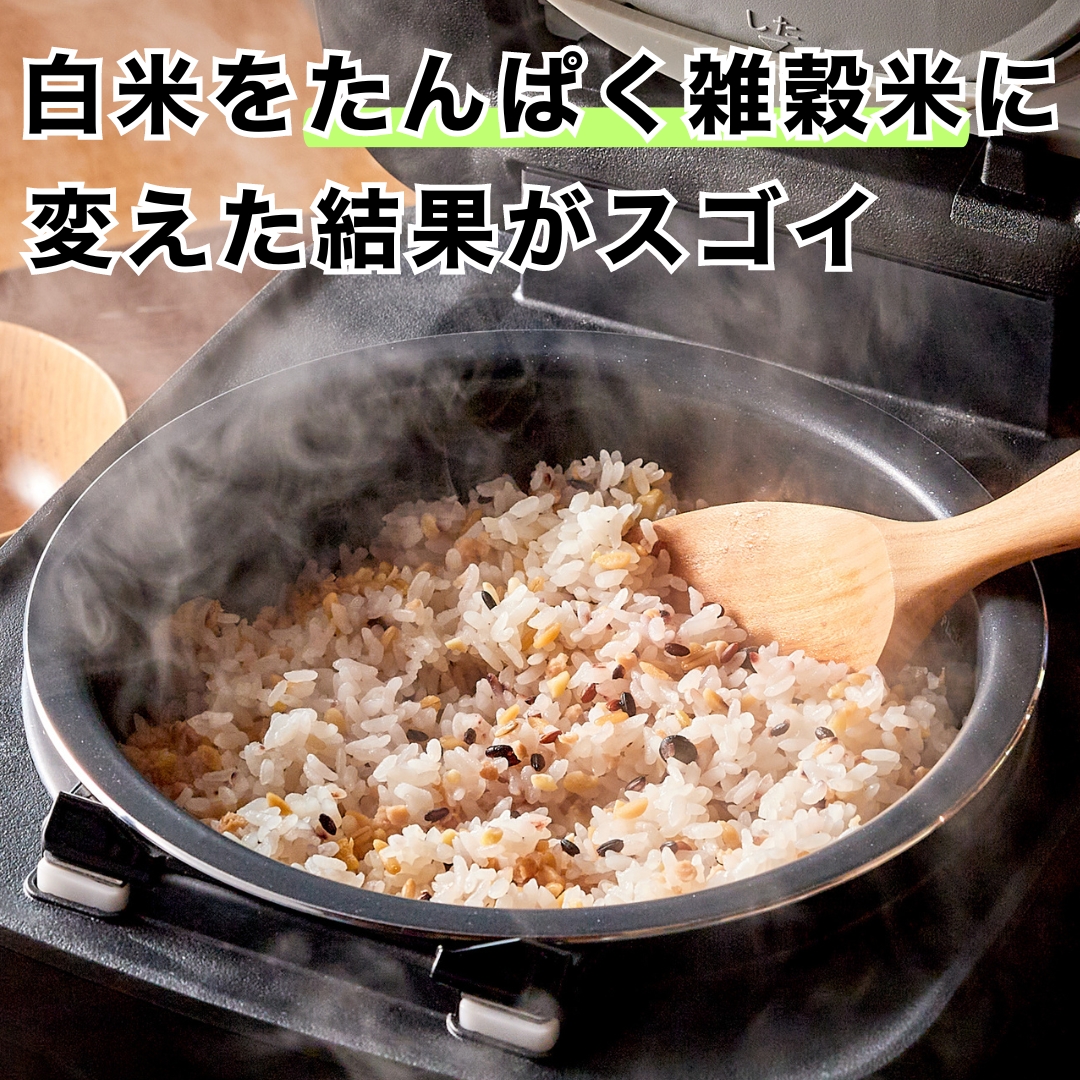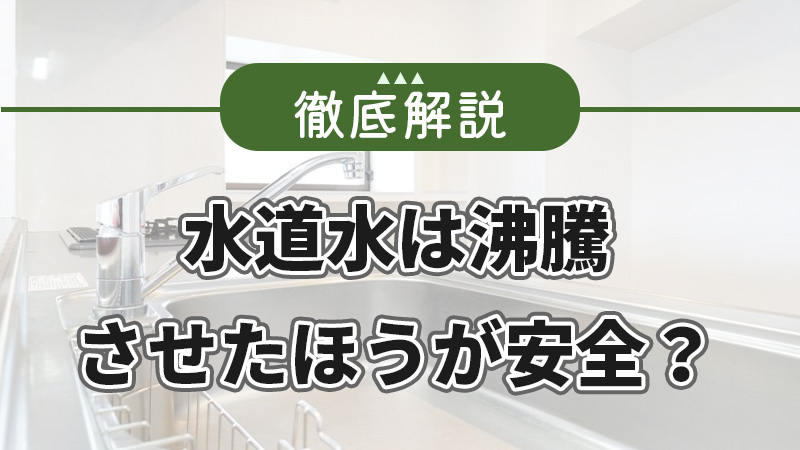「甘酒は飲む点滴」と言われるほど、栄養豊富な発酵飲料として注目されていますが、どんな効果があるのか、またどのように飲むのが最適なのか気になっている方も多いのではないでしょうか?
甘酒には健康維持や美容、ダイエットまで、さまざまな効果があると言われています。
この記事では、甘酒の効果について詳しく解説し、おすすめの飲み方や選び方まで紹介します。

編集部
甘酒を健康的に生活に取り入れたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
甘酒とは?

甘酒は日本の伝統的な発酵飲料で、古くから「飲む点滴」として親しまれてきました。
まずは甘酒の基本情報から、どのような飲み物なのか基本情報を見てみましょう。
甘酒の定義と種類
甘酒は、米や米麹を発酵させて作られる日本の伝統的な甘味飲料です。
甘酒には大きく分けて「麹甘酒」と「酒粕甘酒」の2種類があります。
- 麹甘酒:米麹と米を発酵させて作り、アルコールをほとんど含まない
- 酒粕甘酒:日本酒の製造過程で生まれる酒粕を使って作られるため、微量のアルコールを含む
甘酒は冬の季節限定で楽しむものだとお考えの方も多いですが、一年中楽しめる飲み物です。
麹甘酒と酒粕甘酒の違い
麹甘酒と酒粕甘酒は、作り方も栄養価も異なります。
それぞれの違いは、以下の通りです。
| 項目 | 麹甘酒 | 酒粕甘酒 |
|---|---|---|
| 原料 | 米と米麹 | 酒粕(日本酒の搾りかす) |
| 甘さの特徴 | 酵素による糖化で生まれる自然な甘さ | 砂糖を加えて甘さを調整する場合が多い |
| アルコール含有量 | ほとんど含まれない(0%に近い) | 約0.5〜1%程度を含むことがある |
| 栄養成分 | ビタミンB群、酵素が豊富 | アミノ酸、食物繊維が豊富 |
| 香り・風味 | 米の甘い香りでまろやか | 酒粕特有の香りと風味が強い |
| 飲用の対象 | 子どもや妊婦・高齢者でも安心 | アルコールに注意が必要な人は避けた方がよい |

編集部
健康効果を求めるなら麹甘酒、風味や料理との相性を重視するなら酒粕甘酒と、目的によって選び分けるとよいでしょう。
甘酒に含まれる主な栄養素
甘酒が「飲む点滴」と呼ばれる理由は、その豊富な栄養素にあります。
特に麹甘酒には、ブドウ糖やオリゴ糖、ビタミンB群、必須アミノ酸、酵素など、体に必要な栄養素がバランスよく含まれています。
- ブドウ糖:すぐにエネルギーになる糖質
- オリゴ糖:腸内環境を整える
- ビタミンB1、B2、B6:代謝を促進
- 必須アミノ酸:体の組織を作る
- 食物繊維:腸内環境を整える
- 酵素:消化を助ける
麹甘酒には砂糖が添加されていないにもかかわらず、麹菌の働きによって米のでんぷん質が糖化されるため、自然な甘みがあります。
また、発酵過程で生まれる様々な酵素は、消化を助け、腸内環境を整える働きがあります。
甘酒の健康効果とは?

麹甘酒にはビタミンB群やアミノ酸、酵素など、体の代謝や免疫力をサポートする成分が含まれており、日々の体調管理や疲労回復、便秘解消など、さまざまな効果が期待できます。
ここでは、甘酒がもたらす代表的な健康効果について、詳しく解説していきます。
腸内環境を整える
麹甘酒に含まれる食物繊維やオリゴ糖は善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを改善します。
特に発酵食品である甘酒には、生きた酵素や乳酸菌が含まれており、これらが腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑える働きをします。
実際に、定期的に甘酒を摂取することで、便通が改善されたり、肌の調子が良くなったりした例も多く報告されています。
腸内環境の改善は、アレルギー症状の緩和や、メンタルヘルスの向上にも関連していると考えられています。
疲労回復・エネルギー補給
麹甘酒に含まれるブドウ糖は、最も吸収が早い糖質のため、エネルギー源として素早く利用されます。
特に運動後や疲労時には、失われたエネルギーを迅速に補給できるため重宝されます。
特にビタミンB1は「糖質の代謝」、ビタミンB2は「脂質の代謝」に関わり、これらが豊富な甘酒は、体のエネルギー生産を効率化します。
夏バテや冬の寒さで体力が低下している時、長時間のデスクワークで疲れを感じる時などに甘酒を摂取すると、短時間で体に活力を取り戻すことができるでしょう。
免疫力アップをサポート
麹甘酒に含まれるビタミンやミネラル、アミノ酸は免疫細胞の活性化に役立ちます。
特にビタミンB6は免疫反応の調整に関わり、タンパク質代謝を促進することで抗体の生成をサポートします。
- ビタミンB群による免疫細胞の活性化
- 腸内環境の改善による免疫システムの強化
- 必須アミノ酸による抗体生成のサポート
- 発酵過程で生まれる有益な酵素の供給
また、腸内環境の改善は免疫システムの強化に直結します。
甘酒に含まれる乳酸菌や酵素は、腸内の善玉菌を増やし、腸管免疫を活性化させることで、ウイルスや細菌から体を守る力を高めます。

編集部
特に季節の変わり目や風邪が流行る時期に、甘酒を定期的に摂取することで、体の防御機能を高く保つことができるでしょう。
血糖値の急上昇を抑える
麹甘酒に含まれる糖分は主にオリゴ糖やブドウ糖で、砂糖のようにインスリンの急激な分泌を引き起こしにくいのが特徴です。
また、食物繊維が糖の吸収をゆるやかにするため、血糖値の急激な上昇を防ぎます。
このような特性から、甘酒はGI値(血糖値の上昇速度を示す指標)が比較的低く、糖尿病予防や血糖値管理に配慮が必要な方にも、適量であれば摂取可能な甘味飲料と言えます。
ただし、市販の甘酒の中には砂糖が添加されているものもあるため、原材料表示を確認して選ぶことが大切です。
甘酒の美容効果にも注目

甘酒は健康だけでなく、美容にも効果があると言われています。
ここでは、甘酒がもたらす美容効果について詳しく解説します。
美肌づくりをサポートする
甘酒に含まれるコウジ酸やビタミンB群、アミノ酸は、肌の新陳代謝を促進し、ターンオーバーを正常化する働きがあります。
特にコウジ酸はメラニンの生成を抑制する効果があるため、シミやくすみの予防に役立ちます。
さらに、甘酒が整える腸内環境は肌の状態にも直結します。
腸内環境が改善されると体内の毒素排出がスムーズになり、肌荒れやニキビの改善にもつながります。
髪の毛や頭皮への効果
甘酒は髪の毛や頭皮にも良い影響を与えます。
甘酒に含まれるビタミンB群やアミノ酸は、髪の毛の主成分であるケラチンタンパク質の生成をサポートします。
特にビタミンB6は脂質代謝を促進することで、頭皮の過剰な皮脂分泌を抑え、健康的な頭皮環境を維持するのに役立ちます。
さらに、甘酒に含まれる酵素は頭皮の血行を促進し、栄養素が毛根に行き渡りやすくなるため、抜け毛や薄毛の予防にも効果が期待できます。
内側から髪の毛を健康にしたい方は、甘酒を定期的に摂取することで、徐々に変化を実感できるかもしれません。
アンチエイジング効果が期待できる
甘酒には優れたアンチエイジング効果があります。
甘酒に含まれるアミノ酸や酵素には抗酸化作用があり、体内の活性酸素を除去する働きがあります。
活性酸素は細胞の酸化を促進し、老化の原因となるため、これを除去することで肌のハリや弾力を保つことができます。
さらに、甘酒が整える腸内環境は新陳代謝を活発にし、体内の老廃物の排出を促進することで、全身の若々しさを保つ効果があります。
アンチエイジングのためには、甘酒を長期的に継続して摂取することが重要です。

編集部
美容効果を高めるためには、内側から甘酒を摂取するだけでなく、甘酒パックなど外側からのケアと組み合わせるとさらに効果的です。
ダイエット中にも甘酒はおすすめ?

甘酒は甘いのでダイエット中は避けた方が良いと思われがちですが、ダイエットにも役立つ効果があります。
ここでは、甘酒がダイエットにもたらす効果について解説します。
低脂肪・自然な甘みで満足感アップ
麹甘酒は低脂肪で、砂糖不使用にもかかわらず自然な甘みがあるため、ダイエット中のおやつや間食として理想的です。
通常の甘いスイーツと比べてカロリーが低く、砂糖による血糖値の急上昇も避けられるため、食後の空腹感も抑えられます。
甘酒を摂取することで甘いものへの欲求が満たされるため、チョコレートやケーキといった高カロリーのスイーツに手を伸ばす機会が減り、結果的にカロリー摂取量の削減につながります。

編集部
ダイエット中に甘酒を取り入れる場合は、無糖のものを選び、1日1杯程度を目安に摂取するのがおすすめです。
代謝促進と空腹抑制のメカニズム
甘酒には代謝を促進し、空腹感を抑制する効果があります。
甘酒に含まれるビタミンB群は、糖質や脂質の代謝を促進する酵素の補酵素として働き、体内のエネルギー生産を効率化します。
特にビタミンB1は糖質をエネルギーに変換する過程に関わり、代謝を活発にすることでカロリー消費量を増加させます。
さらに、甘酒の食物繊維は腸内で水分を吸収して膨らむため、物理的な満腹感を生み出し、空腹感を抑制する効果があります。
これらの効果により、適切に摂取することで、無理なく自然にダイエットをサポートしてくれます。
甘酒を飲むベストなタイミングと方法

甘酒の効果を最大限に引き出すためには、適切なタイミングと方法で摂取することが重要です。
ここでは、甘酒を飲むベストなタイミングと方法について解説します。
効果的な摂取量と頻度
甘酒の理想的な摂取量と頻度を知ることで、効果を最大化できます。
甘酒の推奨摂取量は1日あたり100〜200ml程度で、これを毎日継続することで効果を実感しやすくなります。
一度にたくさん飲むよりも、少量を定期的に摂取する方が、栄養素の吸収効率が高まります。
初めて甘酒を取り入れる場合は、少量から始めて徐々に体を慣らしていくと良いでしょう。
また、継続が大切なので、自分の生活リズムに合わせて無理なく続けられる量と頻度を見つけることが重要です。
朝に飲むメリット
甘酒は特に朝に飲むことで様々なメリットが得られます。
朝食前や朝食と一緒に甘酒を摂取すると、腸の動きが活発になり、1日の代謝を高める効果があります。
朝は体温が下がっている状態なので、温かい甘酒を飲むことで体を内側から温め、代謝を促進させることができます。
さらに、朝に甘酒を飲むことで、空腹時の胃腸への負担を軽減しながら栄養を補給できるため、消化器官に優しい朝食の選択肢となります。
朝に甘酒を取り入れることで、1日のスタートを栄養豊富に、エネルギッシュに切り替えることができるでしょう。
寝る前に飲むメリット
就寝前に甘酒を飲むことにも独自のメリットがあります。
寝る1〜2時間前に温かい甘酒を飲むと、体が温まり、リラックス効果が得られるため、良質な睡眠をサポートします。
また、甘酒に含まれるトリプトファンというアミノ酸は、睡眠ホルモンであるメラトニンの生成を促進するため、睡眠の質を向上させる効果が期待できます。
さらに、甘酒の自然な甘みは就寝前の甘味欲求を満たし、余計なカロリー摂取を防ぐ効果も期待できます。
ただし、就寝直前の摂取は消化のために体が活動し続ける可能性があるため、寝る1〜2時間前に飲むことをおすすめします。

編集部
朝と夜、どちらのタイミングで飲むのが良いかは、個人の生活リズムや目的によって異なります。
両方試してみて、自分に合ったタイミングを見つけるのが良いでしょう。
甘酒の選び方とおすすめ商品

市販の甘酒は数多く存在しますが、その品質や配合成分はさまざまです。
ここでは、健康効果を最大化するための甘酒の選び方とおすすめ商品を紹介します。
市販のおすすめ甘酒ブランド
健康や美容効果を期待するなら、質の高い甘酒を選ぶことが大切です。
市販の甘酒の中でも、無添加・砂糖不使用のものを選ぶと、より自然な甘みと栄養を享受できます。
特に麹甘酒は、発酵の力で米のでんぷんを糖化させているため、自然な甘さと豊富な栄養素を持っています。
- マルコメ「プラス糀 米糀からつくった甘酒」
米と米こうじのみを使用し、砂糖不使用・アルコール0%のストレートタイプの糀甘酒です。
自然な甘みで、小さなお子様や妊娠中の方にも安心して飲めます。 - 千代の一番「私は甘酒」
米と米麹のみで作られた、砂糖や酸味料、酒粕、食塩、澱粉を使用していない甘酒です。
サラサラとなめらかな口あたりで飲みやすいのが特徴です。 - 篠崎「国菊 あまざけ」
米と米麹のみで作られた、砂糖・保存料無添加の甘酒。
濃厚な味わいと自然な甘みが特徴です。
これらのブランドは、添加物が少なく、本来の甘酒の栄養と風味を大切にしている点が特徴です。
また、冷凍の甘酒や濃縮タイプなど、保存性や携帯性に優れた製品も増えているので、ライフスタイルに合わせて選ぶとよいでしょう。
原材料表示の見方
甘酒を選ぶ際は、原材料表示をチェックすることが重要です。
健康効果を最大限に得るためには、「米」「米麹」がメインの原材料となっているシンプルな製品を選びましょう。
添加物や保存料、香料などが多く含まれる製品は、自然な甘酒の栄養価を損なう可能性があります。
これらが含まれている場合、カロリーが高くなるだけでなく、血糖値の急上昇を招く恐れがあります。
また、酒粕を使用した甘酒を選ぶ際は、アルコール分の表示にも注意しましょう。
特に子どもや妊婦、アルコールに敏感な方は、アルコール0%または微量であることを確認することが大切です。
手作り甘酒の基本レシピ
自家製の甘酒を作れば、添加物や砂糖を完全に避け、新鮮な栄養を摂取できます。
ご家庭で甘酒を作る場合、最も基本的な材料は「ご飯(白米)」と「米麹」の2つだけです。
炊飯器や保温瓶を使って手軽に作ることができます。
- 材料:炊いたご飯1合分、米麹200g、水200〜300ml
- ご飯と米麹、水を混ぜ合わせる
- 炊飯器の保温モードで6〜8時間発酵させる(55〜60℃を維持)
- 発酵が終わったら冷蔵庫で冷やし、ミキサーでなめらかにする
- お好みで水で薄めて完成
炊飯器を使わない場合は、ヨーグルトメーカーや低温調理器、あるいは保温瓶でも代用できます。
手作りの甘酒は冷蔵庫で4〜5日、冷凍なら1ヶ月程度保存可能です。
自分で作れば添加物なしの新鮮な甘酒を楽しめるだけでなく、濃さや甘さも好みに調整できるのが魅力です。

編集部
甘酒作りが初めての方は、スーパーなどで購入できる「甘酒の素」を使うと、より簡単に手作りできますよ。
甘酒を飲むときの注意点とデメリット
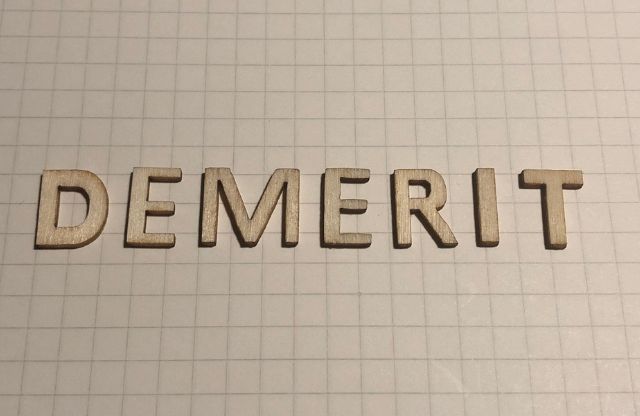
甘酒には多くの健康効果がありますが、摂取する際に注意すべき点もあります。
ここでは、甘酒のデメリットや注意点について解説します。
糖質の摂りすぎに注意
甘酒は栄養豊富ですが、糖質も多く含んでいます。
麹甘酒100mlあたりの糖質量は約15〜20g程度で、これはご飯半膳分に相当します。
甘酒の糖質は主にブドウ糖やオリゴ糖であり、砂糖よりは血糖値の上昇が緩やかですが、大量に摂取すると総カロリー摂取量が増えてしまいます。
また、市販の甘酒の中には砂糖が添加されているものもあり、糖質量がさらに多くなる傾向があります。
甘酒を健康的に取り入れるためには、原材料表示をチェックし、糖質量を把握した上で適量を守ることが重要です。
アルコール入り甘酒の注意点
酒粕から作られる甘酒にはアルコールが含まれている場合があります。
酒粕甘酒には通常0.5〜1%程度のアルコールが含まれており、これは少量でも注意が必要なケースがあります。
特に以下のような方は、アルコール入りの甘酒を避けるべきです。
- 妊婦・授乳中の女性
- 子ども
- アルコールアレルギーがある方
- アルコール依存症の方や断酒中の方
- アルコールと相互作用する薬を服用中の方
甘酒を購入する際は、パッケージに記載されている「アルコール分」の表示を必ず確認しましょう。
アルコールを避けたい場合は、米麹から作られた「麹甘酒」を選ぶと安心です。
また、商品名に「酒粕」と明記されていなくても、原材料に「酒粕」が含まれているかをチェックすることが大切です。

編集部
飲酒運転の原因になることはほとんどありませんが、アルコールテストの直前に酒粕甘酒を飲むと、一時的に反応が出る可能性があるので注意しましょう。
糖尿病や妊娠中の摂取について
特定の健康状態にある方は、甘酒の摂取に特に注意が必要です。
糖尿病の方は、甘酒の糖質量に注意し、医師や栄養士に相談した上で適量を決めることが重要です。
麹甘酒の糖質はブドウ糖が主成分のため、通常の砂糖よりも吸収が早く、血糖値に影響を与えやすい特徴があります。
妊娠中の女性は、アルコールを含む酒粕甘酒は避け、麹甘酒を選ぶべきです。
また、甘酒に含まれる栄養素は妊婦にとって有益ですが、糖質の過剰摂取は妊娠糖尿病のリスクを高める可能性があるため、適量を守ることが大切です。
さらに、食物アレルギーがある方は、甘酒の原材料(特に米や麹)にアレルギーがないか確認してから摂取することをおすすめします。
- 糖尿病の方
血糖値モニタリングを行いながら少量ずつ摂取。可能であれば食後に摂取し、食前の空腹時は避ける。 - 妊婦
アルコールフリーの麹甘酒を選び、1日100ml程度の少量から始める。つわりがひどい時期には、冷やした甘酒が胃の不快感を和らげる場合も。
まとめ

甘酒は日本の伝統的な発酵飲料として、その栄養価の高さから「飲む点滴」と呼ばれています。
この記事では、甘酒の健康効果や美容効果、ダイエット効果について詳しく解説しました。
- 腸内環境を整える:食物繊維やオリゴ糖が善玉菌を増やし、消化機能を改善
- 疲労回復・エネルギー補給:ブドウ糖やビタミンB群で代謝を促進し、疲労回復をサポート
- 免疫力アップ:発酵食品としての特性と豊富な栄養素が免疫システムを強化
- 美肌効果:コウジ酸やビタミン、アミノ酸が肌のターンオーバーを促進
- ダイエットサポート:低脂肪で自然な甘みがあり、代謝促進効果も期待できる
- アンチエイジング:抗酸化作用のある成分が老化の原因となる活性酸素を除去
特に糖尿病の方や妊婦、子どもがいる家庭では、適切な種類と量を選んで摂取することが重要です。

編集部
この記事を参考に、ぜひご自身のライフスタイルに合った甘酒の楽しみ方を見つけてみてください。